ナントカ八景と称してその地域の名所をとりあげたものが各地に存在しているが、その八景の元祖は十一世紀北宋の文人画家・宋迪が画題として選んだ中国湖南省洞庭湖の南にある『瀟湘八景(しょうしょうはっけい)』である。
日本では室町時代、盛んに輸入された中国・宋、元の文化の中でも、特にこの瀟湘八景が多くの文人に愛され、数多くの作品のテーマとなった。
そして日本国内でも、元祖にあやかった八景を選ぼうと試みる人が現れた。古くから有名な「近江八景(琵琶湖)」「金沢八景(横浜)」「木曽八景(長野)」をはじめ多くの八景が、この「元祖八景」を手本にして作られたものである。
近江八景 明応9年(1500)、近衛政家というお公家さんが、「琵琶湖南部」を「洞庭湖南部」に見立てて八箇所の景勝地を和歌に詠んだのがはじまり。
この近江八景が日本で最初に「選定」された八景であるとされている。
金沢八景 元禄7年(1694)、心越禅師という明のお坊さんが、現在の横浜市の能見台から眺めた景色を元祖八景になぞらえて漢詩を作ったことから。歌川広重の浮世絵でも有名。
木曽八景 寛保年間(1740年代)、尾張藩書物奉行の松平君山という人物が作らせたと伝えられる。木曽の絵師池井祐川等によって版画が作られている。
それぞれの「八景」には呼称がつけられている。共通のキーワードで並べてみた。
| 瀟湘八景 | 近江八景 | 金沢八景 | 木曽八景 | ||
| 平沙落雁 | 堅田落雁 | 平潟落雁 | |||
| 遠浦帰帆 | 矢橋帰帆 | 乙舳帰帆 | |||
| 山市晴嵐 | 粟津晴嵐 | 洲崎晴嵐 | 風越晴嵐 | ||
| 江天暮雪 | 比良暮雪 | 内川暮雪 | 御嶽暮雪 | ||
| 洞庭秋月 | 石山秋月 | 瀬戸秋月 | 横川秋月 | ||
| 瀟湘夜雨 | 唐崎夜雨 | 小泉夜雨 | 寝覚夜雨 | ||
| 煙寺晩鐘 | 三井晩鐘 | 称名晩鐘 | 徳音晩鐘 | ||
| 漁村夕照 | 瀬田夕照 | 野島夕照 | 駒嶽夕照 | ||
| 掛橋朝霞 | |||||
| 小野瀑布 | |||||
木曽八景は山の中なので「帰帆」や、水辺に暮らす鳥の「雁」には無理があったようだ。
そのかわり「朝霞」「瀑布」が入って個性的になっているともいえよう。
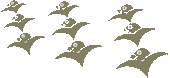
・落雁(らくがん)
水辺に降りる雁の群れ。秋の季語。
・帰帆(きはん)
港に帰る舟。
・晴嵐(せいらん)
晴れた日に山にかかる霞や晴れた日に吹く山風。
・暮雪(ぼせつ)
夕暮れに見る雪景色。冬の季語。
・秋月(しゅうげつ)
天空にある月、水に映る月の場合も。
・夜雨(やう)
水辺に降る夜の雨。よさめ。
・晩鐘(ばんしょう)
夕暮れ時に鳴る寺院の鐘。
入相(いりあい)の鐘ともいう。
・夕照(せきしょう)
夕日に照らされる様子。夕映え。
・朝霞(あさがすみ)
朝にたつ霞。春の季語。
・瀑布(ばくふ)
滝のこと。夏の季語。